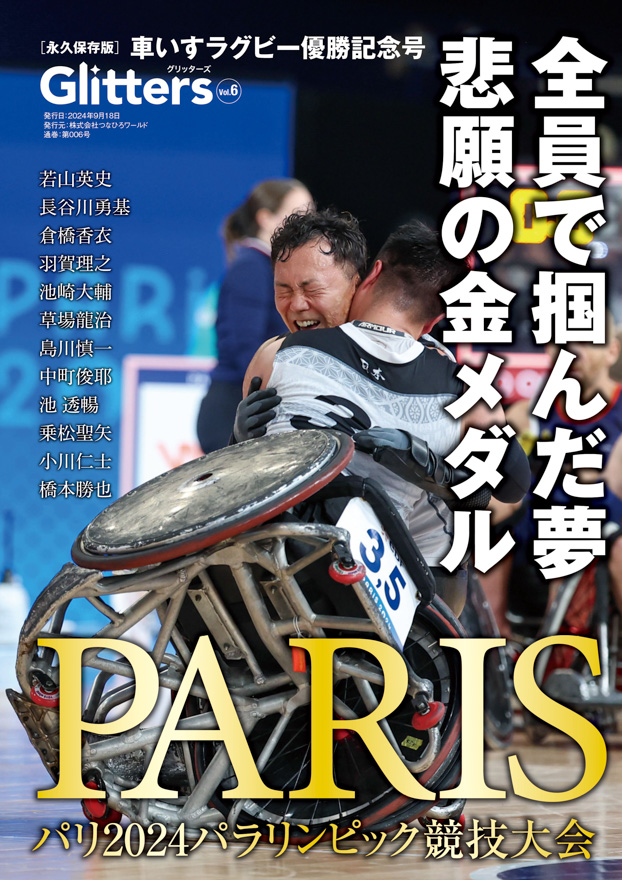中川もえ、12秒47の快走で100m優勝を果たす。
トラック種目では、女子100メートルT47(上肢障がい)で、大学生・中川もえ(西池AC)が、同クラスの第一人者・辻 沙絵(Ossur Japan)に競り勝ち、12秒47で優勝した。
惜しくも追い風参考記録となったが、アジア記録を上回る好タイムに、ゴールした瞬間、中川は驚いた表情を見せ、辻が笑顔で駆け寄り後輩を称えた。
中川が辻に勝ったのは、このレースが初めて。「今日は辻さんに勝つことを目標にしていた。(隣のレーンで走る)辻さんが気になるかと思っていたが、しっかり自分の走りだけに集中できた。これまで日本記録がずっと辻さんの記録で、辻さんも、辻さんの記録も、私にとって壁だった。久しぶりに一緒に走って勝つことができて、とてもうれしいし自信につながった」と喜びを語った。
中川は小学5年生で陸上を始め、中学生のころからパラ陸上に取り組んだ。パラ陸上の世界に飛び込むきっかけとなったのは、辻を紹介する新聞記事を見たコーチから勧められたことだった。
中川にとって辻は「憧れの選手」で、パラ陸上の大会で初めて辻に会えてうれしかった日のことを、今でも鮮明に覚えていると話す。
2021年のアジアユースパラ大会で中川は100メートルと200メートルで金メダルを獲得、2023年にはアジアパラ競技大会で6位入賞を果たした。
自身の競技力が上がっていくにつれ、辻は憧れの存在であると同時に、超えなければいけない「壁」として立ちはだかっていた。
今大会の2週間前には200メートルで辻の持つ日本記録を破った(26秒26)。そして、直接対決となったこの日のレースで、ついにその壁を超えた。
周囲の期待も高まるが、中川には陸上と同じくらい熱意を注いでいることがある。
将来、選手をサポートする側にもまわりたいと看護師を目指している。大学4年生となった今年は実習に国家試験にと学業でも多忙を極める。
陸上か学業か、どちらかにしぼるということはできないと語り、大学院への進学を考えているいま(今シーズン)は、「国際大会にどんどん出場するというよりは、自分の記録を伸ばすことを考えている」と話す。
ただ、アスリートとして、3年後に向けたビジョンもしっかり描いている。
「東京パラリンピックやパリ・パラリンピックを見ていて、やっぱり私もあの舞台に立ちたいという気持ちが大きくなっていった。世界で戦える選手になって、ロスを目指したい」
飛躍への大きな一歩を踏み出した大学生ランナーに今後も期待だ。

辻沙絵が200mで自己ベストに迫る26秒44(追い風参考記録)の力走を見せた
「(中川は)ケガで苦しんでいた時期もあったなかで復活し、こうやって次の世代がどんどん育つのは、すごくうれしい。上肢障がいのクラスがもっと盛り上がればいいなと思っていたので、とてもうれしく感じている。次が楽しみです」
後輩の成長を感じながら、辻自身もこの日のレースでは100メートルを12秒69(※)の自己ベストタイ、200メートルでも26秒44(※)と自己ベストを上回るタイムで走り、順調なシーズンインとなった。(※どちらも追い風参考記録)
パリ・パラリンピックを終え、これまでメインで戦ってきた400メートルから短距離へと主軸を移した。また昨年10月には、「自分と同じような障がいのある子どもたちのサポートをしていきたい」との思いから、義足や義手の世界的メーカーに入社し、新しい生活環境のなか、競技生活を送っている。
「限られた時間のなかで、いかに大切に自分がやりたいことができるか。頭を切り替えて集中し、コーチとコミュニケーションをとりながら短い時間で練習をして、昔より質がよくなったと感じている。これまでとは違うステージになった。自己ベスト更新を目標に、自分がどこまでしがみついていけるかが今のモチベーションになっている」
明るいトーンで語られる辻の言葉は、メンタルの充実ぶりもうかがわせた。
フィールド種目、走幅跳・女子T63(義足・機能障がい)では兎澤朋美(富士通)が4メートル88をマークし、前日の100メートルに続いて、アジア記録を更新。3.5メートルの追い風により参考記録にはなったものの、その後の跳躍では4メートル96の大ジャンプも披露した。
「何年も言い続けてきた5メートルのラインが、やっと具体的に、現実的に見えるところまで来られた。このいい流れのまま今シーズンを走り抜けたい」と手ごたえを口にした。

パリ2024パラリンピック初出場を果たした若生裕太、今大会も安定したパフォーマンスでやり投げ優勝
パリ2024大会でパラリンピック初出場を果たした兄・裕太の背中を追いかけ、昨秋に2歳年下の弟・拳太が、やり投げを始めた。
この日の試合で若生裕太は50メートル79と自己ベストには10メートル近く及ばない記録に終わったが、年明けからの負傷の影響でピークを持ってこられない中、いまできるベストを尽くした。
また、実質的なデビューシーズンを迎えた若生拳太は46メートル44を記録した。
20歳のときにレーベル遺伝性視神経症を発症した兄・裕太は、母系遺伝として自らを責める母への思いからパラスポーツを始めた。目標に掲げてきた東京パラリンピックへの出場を逃し、大きな挫折を経験したが、その悔しさを糧に努力を重ね、パリ大会への切符をつかみとった。
裕太を「自慢の兄」と語る弟・拳太は、自分もいずれ病気を発症するのではないかと覚悟していたという。
「障がいを負ったとき動揺しないようにプランを立てていた。障がいを負っても人生を楽しめると、兄が背中を見せてくれていたので、すぐに気持ちを切り替えられた」
そうして1年半ほど前、障がいを負った弟に「何か打ち込めるものを」と陸上を勧め、兄弟そろっての挑戦が始まった。

若生拳太、兄・裕太の指導を受け着実に力を伸ばし、2位に入賞
「兄弟で日の丸を背負い、世界の舞台で、一緒のフィールドで戦いたい」
それが、ふたりの目標だ。
だが、「日の丸を背負えるところまで、まだビジョンが見えていない(弟・拳太)」と現状は甘くない。
世界と戦うため、まずは国際大会出場への派遣標準記録突破を目指す。
多くの選手にとって、今シーズンの大きな山場となるのが、9月26日~10月5日にインドで開催される「ニューデリー2025 世界パラ陸上競技選手権大会」だ。
パラ陸上では、このあと6月7~8日に「2025ジャパンパラ陸上競技大会」が宮城県仙台市で行われ、世界選手権出場に向け派遣記録突破に臨む。
自己ベスト更新に挑むアスリートたちのパフォーマンスに、今後も注目だ。
(写真・鈴木奈緒、玉城萌華 / 文・張 理恵)
【記録一覧】
●アジア新記録
女子T63 走幅跳 4m96 兎澤朋美(富士通)
●日本新記録
男子T36 100m 12秒03 松本武尊(ACKITA)
男子T34 200m 27秒40 古畑篤郎(アルケア)
男子T37 200m 25秒21 松田將太郎 (長岡AC)
男子T12 100m 11秒22 石山大輝(トヨタ)
男子F62 やり投 20m41 久多良木隆幸(井野辺病院)
女子T11 100m 13秒28 白濱顕子(ライオン事務器)
女子T14 100m 16秒35 岩本めぐみ(近畿パラ陸協)
女子T20 200m 26秒00 加藤茜(野村不動産)
●大会新記録
男子T20 1500m 3分55秒12 十川裕次(オムロン太陽)
男子T37 1500m 4分24秒94 井草貴文(ACKITA)
男子T52 200m 30秒72 伊藤智也(バイエル薬品)
男子T34 800m 1分48秒95 古畑篤郎(アルケア)
男子T64 走幅跳 6m58 田巻佑真(アシックス)
男子F34 砲丸投 6m26 鈴木雅浩(北海道東北パラ陸協)
男子F42 やり投 25m50 鈴木貴之(横手パラ)
女子T35 100m 17秒89 佐伯菜々美(帝京大)
女子T37 100m 15秒10 井門結(聖カタリナ高校)
女子T13 200m 26秒23 佐々木真菜(東邦銀行)
女子T20 走幅跳 5m17 川口梨央(NPOかがやき)
【陸上】
一般の陸上競技と同じく、「短距離走」「中距離走」「長距離走」「跳躍」「投てき」「マラソン」と多岐にわたった種目が行われる。
障がいの種類や程度に応じて男女別にクラスが分かれ、タイムや高さ、距離を競う。選手たちは、「義足」「義手」「レーサー」(競技用車いす)など、それぞれの障がいに合った用具を付けて、パフォーマンスを磨いている。
用具の進化によって、選手のパフォーマンスが上がっていることは事実だが、決して用具頼りの記録ではない。用具を使えば技術が上がるわけではなく、選手には使いこなすだけの身体能力、筋力、バランスなどが必須となる。
視覚障がいのクラスでは、選手に伴走する「ガイドランナー」や、跳躍の際に声や拍手で方向やタイミングなどを伝える「コーラー」などといったサポーターの存在も重要となる。選手とサポーターとの信頼なくしては成り立たず、息の合ったやりとりはふだんの練習の賜物でもある。
クラスによっては、オリンピックにも劣らないレベルの記録が出るなど、時代とともにレベルが高くなっており、毎大会トップ選手の記録更新が注目されている。多種多様な障がいの選手が一堂に会し、さまざまな工夫を凝らし、自分自身の限界に挑む姿が見られるのが、この競技の魅力でもある。
一般の陸上競技と同じく、「短距離走」「中距離走」「長距離走」「跳躍」「投てき」「マラソン」と多岐にわたった種目が行われる。
障がいの種類や程度に応じて男女別にクラスが分かれ、タイムや高さ、距離を競う。選手たちは、「義足」「義手」「レーサー」(競技用車いす)など、それぞれの障がいに合った用具を付けて、パフォーマンスを磨いている。
用具の進化によって、選手のパフォーマンスが上がっていることは事実だが、決して用具頼りの記録ではない。用具を使えば技術が上がるわけではなく、選手には使いこなすだけの身体能力、筋力、バランスなどが必須となる。
視覚障がいのクラスでは、選手に伴走する「ガイドランナー」や、跳躍の際に声や拍手で方向やタイミングなどを伝える「コーラー」などといったサポーターの存在も重要となる。選手とサポーターとの信頼なくしては成り立たず、息の合ったやりとりはふだんの練習の賜物でもある。
クラスによっては、オリンピックにも劣らないレベルの記録が出るなど、時代とともにレベルが高くなっており、毎大会トップ選手の記録更新が注目されている。多種多様な障がいの選手が一堂に会し、さまざまな工夫を凝らし、自分自身の限界に挑む姿が見られるのが、この競技の魅力でもある。